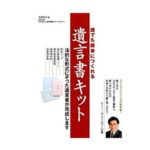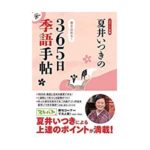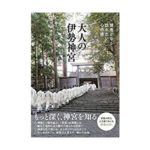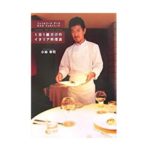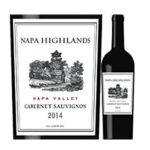3月6日放送の「この差って何ですか?」では「贈り物に熨斗(のし)を付ける時と付けない時の差」をクイズ形式で出題!贈り物を買う時に店員さんに「熨斗は付けますか?」と聞かれて、熨斗を付けたら失礼に当たるのでは?と考えすぎてしまっている方も多いと思います。誕生日、就職祝い、謝罪、結婚・出産、還暦、お葬式と6つのシチュエーションで熨斗を付けても大丈夫かどうかをわかりやすく解説してくれました。
今日も観てくれて、ありがとうサ❤❤
Facebookの集合写真は、別バージョンサ!Facebookもチェックしてサ!
次回は3月13日(火曜)よる7時から放送サ😃❗来週もお楽しみにー🙌🏻#オカダ・カズチカ#佐藤仁美#松本明子#川田アナ#川田裕美#上地雄輔#tbs#この差#この差って何ですか? pic.twitter.com/bY1ucHUcot— TBSこの差って何ですか? (@konosa_tbs) 2018年3月6日
熨斗をつけても良いシチュエーションとは?
熨斗をつけても問題ないのは、誕生日、就職祝い、結婚・出産、還暦、謝罪、ほとんどのシチュエーションで熨斗を付けても大丈夫です。熨斗はめでたい時に付けると思いがちですが、実は「相手を敬う気持ち」を表すために付けるもの。謝罪の時でも相手を敬う気持ちが大切なので熨斗は付けた方が良いとの事です。そして唯一熨斗を付けていけないのはお葬式、この理由には熨斗が生まれた理由が深く関係していました。
熨斗が生まれた理由
熨斗の風習が始まったのは奈良時代、当時は天皇に農作物や特産品を献上するのが習わしでしたが海の近くに住む人は獲るのが命懸けだったので数が少なく貴重な「アワビ」を献上していました。しかし獲ったアワビを天皇に献上しようとしても腐ってしまって献上品になりません、そこで考えられたのがアワビを使った干物でした。
アワビを細長く切って熱した鉄で薄く延ばしてアワビの干物を作って献上しました、薄く延ばす事を熨す(のす)と言いますが伸ばしたアワビは「熨しアワビ」と呼ばれました。この「熨しアワビ」が非常に貴重で相手に対する敬意を表すモノとして定着して、贈り物には「熨しアワビ」を添える風習が広まっていったのです。
現在の形になった理由とは?
江戸時代にはより相手に敬意を表すように熨しアワビを紙で飾り付けるようになりました。そして時が過ぎて昭和の時代、戦後の物不足やアワビが高価だったために贈り物には印刷した「熨しアワビ」をつけるようになりました。熨斗とは紙全体を表しているのではなく小さなエンブレムのような形をしている部分だけが熨斗です、紙は「のし紙」といってアワビを飾り付けるためのものです。
なぜお葬式のお供え物や香典返しには付けてはいけない?
その理由は熨斗がアワビの干物を指している事が理由です。仏教では動物を殺生したモノは出してはいけない決まりがあります、熨斗はアワビを殺生して作ったものなのでお葬式にはそぐわないという事になります。お葬式の場合は熨斗の部分が削られた「掛け紙」を使うのが一般的、熨斗をつけても良いかどうか迷ったら「掛け紙」をして贈り物をすれば何も問題ありません。
感想&まとめ
昔はお見舞い時にも熨斗を付けていたそうですが、最近では「病気が延びる・入院が延びる」という縁起が悪い事に繋がるので熨斗は付けないようにする方が一般的だそうです。時代や人の考え方によってマナーはどんどん変わっていきますが、人の失礼に当たらないくらいの最低限のマナーは覚えておきたいものですね♪